令和7年6月24日(火)16時25分から南風館で、法人内部研修が行われました。
今回のテーマは自然災害と感染症対策の「BCP策定」で、今回は自然災害対応を通所型福祉サービス事業所としての対策をワークテーマにして実施しました。
そもそも、「BCP」とは何か、昨年度もこのテーマで法人内部研修を実施していますから、復習の意味で何人かに聞いたのですが、残念ながら答えられない方が若干おられました。
復習の意味で、再度紹介します。『BCP(事業継続計画)とは、自然災害や感染症の流行などの緊急事態が起きた際に、被害を最小限に抑え、速やかに事業の回復を図るための計画のこと。詳細については後ほど紹介しますが、業務における優先順位の決定、具体的な対策の検討などを経て、策定します。』


今回は自然災害が発生したときの対応を通所型障害福祉サービス事業所であるユートピアとして、どういうことを考えておかなければならないかを、ワークテーマにしてグループ討議しました。
- 大地震が発生し、家族へ連絡・引き渡しを実施しようとした場合、どの様な問題が生じると考えられるか?
A施設側の問題 B利用者家族側の問題 Cインフラの問題
- 利用者が到着後に大地震が発生し、利用者の当日中の帰宅が困難になった時、滞留者の支援として必要な業務を整理しよう。(水・電気・ガス・固定電話のライフラインは途絶している状況として想定する。)
・継続業務 ・追加業務
この①、②について考えられることをグループごとに話し合い発表しました。
その後の対策などの話し合いは7月のスタッフ会議への宿題として研修を進めました。
参加者からは様々な意見が出ておりましたが、押しなべて同一の答えに集約されていました。
ここでは、この研修の元資料から回答とされている事例を紹介しますので、今後の参考にしていただければと思います。記事が長くなっていますが、この研修の受講資料と捉えてみていただければと思います。
- 大地震が発生し、家族へ連絡・引き渡しを実施しようとした場合、どの様な問題が生じると考えられるか?
A 施設側の問題
・携帯電話もなかなかつながらない
・どれが最新の連絡リスト?
・何を伝えればいい?とりあえず迎えに来てもらえればいいかな?
・それともいつも通りの時間に送った方がいいかな?
B 利用者家族側の問題
・事業所から連絡はないけど、うちの家族(利用者)は無事かな?
・こちらから電話してみようかしら?
・会社に出勤しているけど、電車が止まっているからいつも通りの時間に送られても
間に合わない・・・
C インフラの問題
【東日本大震災の被害状況】
・固定電話の復旧には、1ヶ月以上の期間を要した地域もある。
・携帯電話は一部地域では不通になったが、ほとんどの地域では使用可能であった。
ただし、通信制限がかかり繋がりにくい状況が続いた。
≪ワークテーマ1解説≫
利用者の引き渡しについて
・送迎車を使用して自宅に送り届ける場合は道路状況等を確認し、慎重な判断が求められる。
また、渋滞や通行止めなどにより通常より大幅に時間がかかる可能性があること、
ガソリンの入手が困難になることや余震の危険性等を勘案し判断する必要がある。
・送迎中に発生した場合の対応についても(事業所に引き返す等)検討すること。
・ご家族等に事業所に迎えに来てもらう場合は、引き渡し場所や確認名簿等の整理を
しておく。
連絡について
・災害時には固定電話等、通常使用している連絡手段が使用できない場合があるため、
複数の連絡先・手段を確保しておくことが望ましい。(携帯電話・SNS等)
[利用者氏名・緊急連絡先①(母、自宅固定)・緊急連絡先②(母、携帯)・
緊急連絡先③(父、携帯)・緊急連絡先④(母、メール)]など
・連絡が付かない場合、事前に事業所としての対応ルールを決めておくことで、
利用者家族等との共通理解があり、混乱を抑止することができる。
例)震度6弱以上の地震の場合は、原則家族から連絡する等
・災害発生時において個別に連絡が取れない場合は事業所ホームページに対応方針を
掲載する等の対応も検討しておく。
引き渡しのルール設定について
・利用者引き渡し方法について、災害時に個々の要望に応じることは現実的でないため、
事業所としての引き渡し方法に関する方針を明らかにする。
例)震度6弱以上の地震が発生した場合は、車両による送迎を中止し、原則家族等に
迎えに来ていただき、引き渡すこととする。
・送迎中に発生した場合の対応についても(事業所に引き返す等)検討する。
特に、連絡が取れない状況下においては、現場のみの判断で行動することが無いよう
ルールの設定が重要。
・ご家族等に事業所に迎えに来てもらう場合は、引き渡し場所を予め周知しておくことや
確認名簿等の整理をしておく。
参考 一人暮らし利用者の帰宅判断について
・主な判断ポイントとしていかが考えられる。
✓余震の危険性(地震の場合)
✓利用交通機関の稼働状況
✓帰宅経路の安全状況
✓自宅及び自宅周辺のライフラインの被害状況
✓利用者本人を取り巻く支援環境の被害状況
✓利用者本人のイレギュラーな事象への対応力 等
・ご本人やご家族、成年後見人等と非常時の対応について事前に協議しておくことが重要。
- 利用者が到着後に大地震が発生し、利用者の当日中の帰宅が困難になった時、滞留者の支援として必要な業務を整理しよう。(水・電気・ガス・固定電話のライフラインは途絶している状況として想定する。)
・継続業務
医療的ケア
見守り
排せつ介助
環境整備
労務管理
・追加業務
安全確保・避難
利用者・家族への連絡・情報提供
物品確保
食事支援
怪我人の手当て
建物・設備の被害点検
継続業務については、通常業務の流れのタイムスケジュールを作成し、一覧になっている業務を
「休止・宿所・継続」というように分けてお優先順位を付けておく。
・追加業務
上記の業務を中身により詳細に分類にしておく。
例)夕食支援・服薬支援を含む医療的ケア・災害トイレの設置及び使用の支援・電力確保・
他事業所への応援・非番職員の安否確認、連絡・利用者家族への連絡・利用者家族への
引き渡し・負傷者の病院搬送・備蓄品の確認・水の確保・寝床の確保・建物、設備の
被害点検危険区域の立ち入る禁止措置・地域貢献等
滞留者の支援として実施すべき業務を提供するにあたり、事前にどのような準備や備蓄が必要か?
・災害時においては、ライフラインの試用が限定されている状況で、いかに優先業務を
実施するか検討しておくことが重要
・優先業務を実施するうえで必要な設備・備品を明らかにし、災害時に使用できないことが
想定されるものについては代替・代用手段を明らかにする。
・特に継続業務は、普段使用している設備や備品が使用できない可能性が高いことに
留意する。
例)水道 停電・断水時⇒ペットボトル
照明 停電時⇒LED型ランタン、懐中電灯 等
・変更、追加をした業務手順を検討し明確にしましょう。
これらの問題提起をどのように解決するか、想定できることの事前の準備や協議がこれから必要に
なってきます。




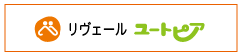
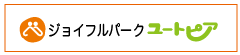
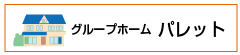
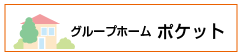
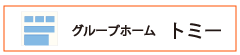
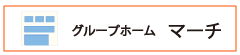
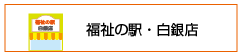
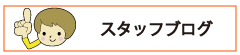
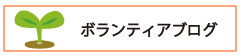
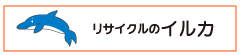
コメント
コメントする
コメントする場合 ログイン してください。