久しぶりに会った子供の学校のお母様から理不尽に思った(;^_^Aこぼれ話が…
お子さんが通所しているうちの一つの施設が
お子さんの障がいの程度を決めつけ
型にはめる支援を押し付けている感が強く
お子さんに対し求める理想が大きすぎる…と
意見しようものなら辞めてかまわないという話を臭わすと…( ̄▽ ̄;)
耳を疑うような話ですが… 近隣市町村、施設は沢山あれども
残念ながらそのような事を言う施設もないわけじゃない…💧
一番の問題は通所する施設によって支援が違い過ぎて子供が戸惑っている…
という事だ。 話を聞いて思うのは、そこには相談支援員が噛まなければならない
『 支援会議 』も必要となってくる
その『支援会議』だが、話をすると大抵のお母様が尻込みをすることが多い…
「学校や施設で子供が困ったことになるのでは?」 「職員にどう思われるか?…関係性が心配」
「だからそこまでしなくても…」と
果たしてそうであろうか?
お子さんの気持ちを一番感じる事が出来るのは一番身近な家族(キーパーソン)
キーパーソンはしっかりと子供の代弁はしていく必要があります
学校、施設、家庭で支援がバラバラ過ぎては
多感な子供時代を落ち着いて過ごすことが難しい…
お子さんの特性によっては家庭や学校、各施設が三位一体となっての支援が必要
定期的に各施設職員が直接顔を合わせて話合いをすることで
お互いの良い所を取り入れて支援を充実させることも出来る
もちろん、親の方も家庭以外での子供の様子を垣間見る事が出来、
関わる学校や施設の職員が『気づき』をする意味でも重要な場面であろうかと思うのです
以前、支援会議開催に学校側が難色を示した… との内容のブログが掲載されました
数年、支援会議を実際に行っていて思うのは、
一見、専門的と思われる学校、施設でも
担当者が不慣れであったり経験が無かったり…、様々あります
学校自体、経験がなく不慣れな場合は、
親が強く発信しなければならないのは何年たっても… 今も昔も一緒かもしれません
相談員と親は2人3脚 (;^_^A頑張って下さいね~🚩
☆追伸
こぼれ話をしてくれたお母様に
「PRではないけど、ユートピアにも放課後等デイサービスがあって、ブログを観るといい感じだよ」
「主に集団療育をやっているけど一度見学してみたら」と触れてみました。
そのお母様、「ユートピアに上の娘の同級生のお母さんがいる」と言っていました。
相談があったらよろしくお願いしますね~^^v💕

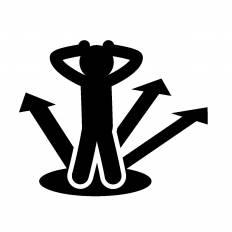

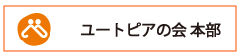


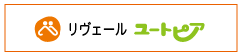
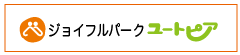
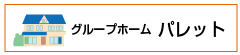
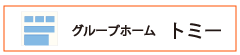
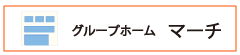
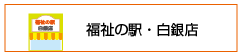
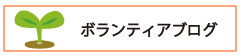
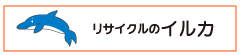
コメント
コメントする
コメントする場合 ログイン してください。