利用者Kさんが悩んでいる。思えば性格的に悩んでいない時はほぼ無く、年中何かしら悩み事を抱えている。その中でも波があり、まずまず安定して過ごしている時と、助けて欲しいとアピールしてくる落ち込みの時期がある。スタッフ会議でも幹部会議でも、Kさんのことを話題にあげた。日々作業や日課を通してもっとも身近で支援しているスタッフが口を揃えて、「今はまだ手を差しのべる時ではない。」と断言する。Kさんが持っている自己解決能力を信じた発言。相談したいのに相談相手がいないと言うKさん。自分の思う答えが返って来ない場合、Kさんの中では相談したことにはなっていない。『わがままなとらえ方』そう思われても仕方ないが、そういったもののとらえ方をしてしまうのが紛れもないKさん。「支援スタッフはあなたのことを理解して、信じて見守ってくれているよ。必要があれば手を貸す準備もしているよ。」そう諭すが、腑に落ちない表情。利用者が混乱しないように、スタッフ間で共通認識を持って一貫した支援を行う。大切なことではあるが、受け手がどう感じ取るかを常に考えた対応を心がけなければ、冷たく高い壁になってしまう。
コメント
コメントする
コメントする場合 ログイン してください。

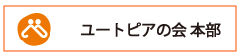


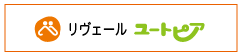
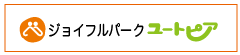
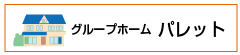
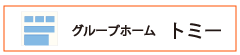
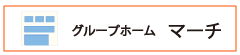
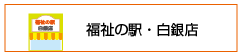
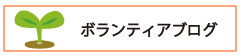
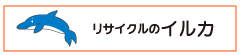
同じことばで話したつもりでも、人によって受取方って違うものですね。
また、伝えた相手が話したことばの真意が、それを受け取った相手に
届かないこともよくあることです。
「いますぐあなたの思うようにはいかないことが多いだろうけれども、
あなたの気持ちはよく分かりましたよ」と相手に伝わるように、一度は受容してあげることが、大切なのではと私は思います。