行き場の無い閉塞感に、つい浮かんだのは横浜の赤い靴だった今ではあまり聞く事が無いこの詩に重なる様な現実は身近な所で起きている。母親の末路を看る立場に立たされた彼はには入り組んだ複雑な人生は理解できる筈も無いがその義務感だけには忠実である。
既に就職した彼であるが部下の生活指導員から彼の事で相談を持ちかけられたのである。それは重身で病棟にいる身内の無い母親の後見人の事であった。勿論業務外の事でありその結論に言葉が詰まった。しかしその眼は意を決した事を表していた。その後病院の対応等彼と行動した報告を受け方向性が定まったのは確かの様であるが、最終的には墓地に辿り着く事になる。ここからは自分が動くしかないと晴れた日曜日に彼の断片的な記憶を辿りながら祖母の墓を探し確認出来た、しかしその墓の施主とどんな関係があるのか判らない、そんな中で写真アルバムの中から手掛かりを見つけた。次の目的が見えやれやれであるが彼の複雑な人生は小説でも明かせないと悟りむしろ横浜の赤い靴のストリーに写しだされら似合うかも知れない。
人との関わりは苦痛である時もあるがそれを感じない環境に身を置く生活は客観的であるが自由である。そこには自ら支援を求める事が無い事が想像出来る

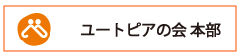


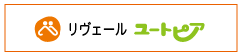
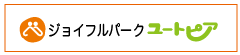

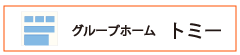
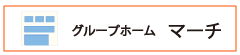



コメント
コメントする
コメントする場合 ログイン してください。