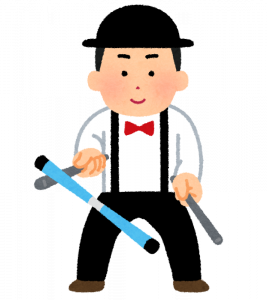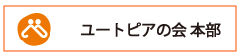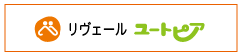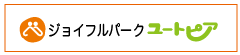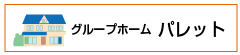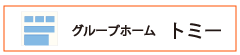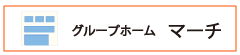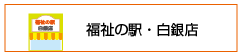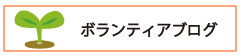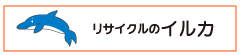» 未分類のブログ記事
おばんです、今は寒波らしくマイナスの気温が続いていますね。
毎日寒くてしんどいです🥶
さて、1日経ちましたが
「新年の集い」どうでしたか?
結構盛り上がっていた気が?します🙆♀️
成功では?と自分なりに思いました😌💭
前半の司会のKさん
たくさん練習しました。
イントネーションだったり読む速さだったり
スタッフからアドバイスを受けながら頑張りました💮
何度「もう少しゆっくり」と言ったことか、、、
練習の成果が出たのではないかと思います😊
人前に出るのが苦手なKさんですが、今では「大丈夫」という程になりました!
この司会をお願いする時には「やってみる」「大丈夫」と話していました😌
Kさんにお願いして良かったです。
お疲れ様でした🫡
こんにちは、リヴェールスタッフMです。
このところ毎日、気温が氷点下で路面が悪く運転には気を使っている方がたくさんいると思います。時間には余裕を持って行動しましょう。
さて、昨日1月24日はユートピアの会の新年の集いが開催されました。ご来場してくださった保護者の方々、来賓の方々、利用者の方々ありがとうございました。そして、スタッフのみなさん、お疲れ様でした。
そんな中、各事業所から作品展示がありました。リヴェールからも「輪」という書道の作品が展示されました。
書道と言えば、ホワイトハウスで作業をしているMさんですが、今回は今までと少し違い大きいサイズの紙に一発勝負で書かなくてはいけません。
普通の半紙で練習するも、本番用とはサイズが違うため何度もイメージトレーニングを行っていました。
 ➡飾り付け前の撮影
➡飾り付け前の撮影
ですが、この通り見事、立派に書きあげました。
Mさん、ありがとう。
こんにちは心技体です。
今日は様々な方からブログ内で紹介された「新年の集い」でした。
利用者さんや保護者様、ご来賓、理事の方々をお招きしての新年会と言う事で、ものすごく盛り上がりました。
まず初めにジャグリングパフォーマーの「アット」さんが、とても引き込まれる素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。利用者さんも見せ場毎に「おー・・・わぁー・・・すごい」など言葉が出ており、見入っていました。
パフォーマンスが終わった後は楽しかったと声が出てアンコールの声も多く上がり、とても難しいとされる、ボール7つでのジャグリングも見事成功となり、大変盛り上がりました。アットさんありがとうございました。
その後はゲームや新年開運おみくじ等様々あり、とても笑顔溢れる新年会だったと思います。
集いの写真は現在準備の真っ最中です。今後様々な方のブログでupされると思いますので楽しみにしていてください。
まだまだ寒い時期ではありますが、春に向けてさらに頑張っていきますので、今年もよろしくお願いいたします。
仕事中に指を欠損する大事故で障がい者になったOさん。以前このブログでも紹介をしましたが、11月からA型事業所を継続して利用しています。
A型事業所では、野菜の出荷に伴う作業を行なっていますが、生鮮品を取扱うため気温が低めの作業環境で作業をしております。そのため、障がいをおった手は全く感覚がなくなり、気がつけば出血したり、しもやけのような感じにもなる事もあると教えてくれました。
だけど仕事は妥協したくない、雇ってもらっているのだから、できない、やりたくないとわがままは言えないと話すOさん。
こちら側としては、わがままではなく障がいを負った手が怪我や化膿したりする事が一番の問題だと思い、OさんにA型事業所とはどんなところかを再度説明しました。すると、教えてもらえて良かったと話し…本当はこの職種は好きで選んだのだけど、手の事を考えたら、控えたい作業もあり、A型事業所ってどんなとこかという話が聞け、気持ち的にも楽になりましたとおっしゃっていました。事業所のスタッフには直接伝える事が出来なかった事をモニタリングを通して相談員、事業所スタッフにも伝える事ができました。結果、作業配慮をしてもらう事になりました。
次回のモニタリングでどのように変化をしているのかが楽しみです。
…Oさん、出会った時は眉間にシワを寄せてオドオドしていましたが、モニタリングで会ったOさんは全く別人、表情が明るく雰囲気が違う。つい私も、いい表情していると伝えると、息子さんにも正月に会った時に、仕事を始めてからいい顔をしている、明るくなったと言われたんだよと教えてくれました。さすが息子さん!!母の事を一番心配し、一番分かっています。